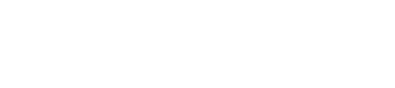私たちのミッション
ビジョン
子どもたちに「数のセンス」を。
私たちは、そろばんを通じて子どもたちに「数を感じる楽しさ」と「自分で計算する自信」を生み、集中力や持久力、論理的思考能力を育み、「未来へ生きるチカラ」を養う活動を続けています。
私たちの取り組む課題

きっかけ
ある公立小学校の依頼を受け、小学3年生と4年生の児童を対象に、そろばんの出前授業を行ったことから、小学校の算数授業が抱える課題を知り、子どもたちの計算力を鍛える一助となれるのではと、継続した事業として行うためNPOを立ち上げ、行政の認可を受けました(法人番号5120005017634)。現在は約80の小学校で、オリジナルの教材や動画解説などを使用し、そろばんの歴史や基本的な名称等から始まり、カリキュラムにそって授業を提供しています。

課題の背景
文部科学省の学習指導要領「生きる力」によると、小学校の3年生と4年生の算数では、「筆算を重視しつつも、そろばんや具体物などの教具も適宜用いる」ことが求められています。特にそろばんは、単なる計算手続きではなく、「なぜそうなるのか」という数の構造的理解を助ける道具でもあり、数と計算の「意味理解」の促進に役立つものです。ITが進化する現代において、論理的思考のもとに活用する計算力は子どもたちの「生きるチカラ」となり、一生役立つ武器になるといえます。
私たちは、経験豊かなそろばん講師を小学校へ無償で派遣し、子どもたちに体系立てたそろばんの仕組みや計算方法を教えています。
なぜ、この課題に取り組むのか

計算力の重要性と文化として
現代の教育現場においてはそろばんを習った経験のない教員も多く、文科省の要件を満たす算数授業ができないケースや、ITの発達などにより計算力そのものが軽視され、外国語授業と天秤にかけ外されるなど、自治体レベルで判断されるケースなどもあり、算数や数学の土台となる計算力が備わりきらずに成長し、学力の伸び悩みを生じさせているケースを解決したいと考えるからです。
また江戸時代から昭和にかけては、子どもたちは習い事といえば「読み書き算盤」というシンプルな学び文化がありましたが、それが時代とともに消えていくのでは、集中力や脳の持久力、また学びを楽しく競い合う機会の減少にも繋がってしまうという危機感もあるため、学び文化の継承との思いから取り組んでいます。
出前授業で、そろばんの楽しさを子どもたちに。
子どもたちは、初めて触れるそろばんに目を輝かせ、「またやりたい!」と喜んでくれます。
| 出前授業の内容 | 対象学年:小学3年〜4年生 |
| 実施回数:各小学校と打ち合わせにより決定 | |
| 内 容:そろばんの歴史や文化的背景の講義、そろばんを使った計算練習の実技。 | |
| 実施地域 | 大阪府下の小学校 (約80校の小学校で実施実績) |
| 出前授業の目的 | 非認知能力(集中力・記憶力・自己肯定感)育成 |
| デジタル時代だからこそ求められる「手で考える学び」 | |
| そろばん文化の継承(文化保護・次世代教育) |
そろばんによって指を使って考えることで、脳が活性化され集中力・記憶力・忍耐力を自然と養うことに繋がっていきます。そしてデジタル時代において、0と1の間にある「アナログ思考力」を育成することが、子どもたちの生きるチカラとなります。ひいてはこの活動が日本の伝統文化を次世代に伝える意義あるものと信じ、これからも子どもたちの未来に、そろばんを繋いでいきたいと考えています。
でも、資金が足りません。
各小学校への講師派遣には、移動費や謝礼などが発生するため、活動の継続には資金が必要です。1回の訪問で約1.5〜2万円、年間40校で80万円が必要となります。
| 寄付金の使徒 | 講師謝礼(1回あたり1〜2名) |
| 交通費・運搬費 | |
| 教材費(1回あたり30〜40セット/1クラス) | |
| 事務局運営費(実施報告書の作成・報告活動) |
どうか、未来の子どもたちの「数の力」を育むために、あなたの力を貸してください。
気になるNPOを支援できるサイト「Syancable」でもご寄付いただくことができます。